|
8.タル・ベーラの映画 2012年4月3日。強風が吹き荒れている。木々の枝を揺らす風の音が"ヤンの小屋"を包囲する。窓ガラスを揺らす音。時々何かが飛ばされ、どこかに当たる。 |
|||||||
| 「タル・ベーラは、今生きている最も優れた映画監督だ」と、町田純は言っていた。 | |||||||
 |
|||||||
| 彼と見に行った最後の映画はタル・ベーラの「倫敦から来た男」だった。ガラス張りの制御室から目撃した殺人事件。転轍機の音が神経質に響く。 | |||||||
| 最初に見たタル・ベーラは「ヴェルクマイスター・ハーモニー」。 | |||||||
 |
 |
||||||
| 巨大な鯨の剥製とともに扇動者がやって来る。はっきりとしない不満にくすぶる人々は、無意識に扇動者を待ち望む。無言で病院の襲撃に向かう人々の列を、カメラは長いワンシーンで延々と坦々と追う。「これは今までに見た最も恐ろしい行進だ」と町田純は言っていた。人々の心に潜むファシズムの恐ろしさ。 | |||||||
| そして、もう純のいない昨年の夏、台風が東京を直撃した日に一人で見に行ったのが、「サタンタンゴ」。上演時間7時間半のタル・ベーラ作品。うらぶれた村に「死んだはずのあの男が帰ってくる」と噂が流れる。そうしたらこの金も取られてしまうだろう。金を持ち逃げする計画を立てていた村人も、何故か逃げずに留まっている。誰からも顧みられなかった少女の死のエピソードを挟んで、あの男たちが帰ってくる。村人達は魅入られたように男の言葉を信じ、金を差しだし、一切を捨てて男に従う。またもや扇動者を待つ人々。この単純な物語が複数の人物の視点で、重層的に描かれる。 どの作品もモノクロームでワンカットが非常に長いのが特徴だ。 しかし、飽きることはない。表現には、それなりの時間が必要な場合もあるのだと納得する。長いワンカットの場面に引き込まれながら、次は何が現れるか?と、期待と緊張で画面を見つめる。こんな映画体験は、タルコフスキーの映画以来だ。 貧しい人々と荒んだ風景ばかりで美しい場面もないのだが、でも美しい。「ヴェルクマイスター・ハーモニー」の郵便配達の若者の姿、田舎の町のたたずまい、「ニーチェの馬」の父と娘が毎朝身に着ける服、「倫敦から来た男」の制御室……モノクロの画面全てが美しい |
|||||||
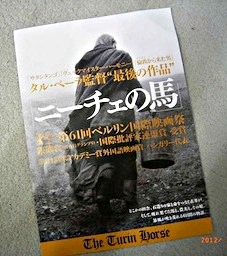 |
|||||||
| 「ニーチェの馬」は監督自身が最後の映画であると宣言している。 これ以上作っても、今までの作品と同じような発想しか出て来ないであろう、というのが理由だ。やはり、タル・ベーラはすごい! 最後の作品「ニーチェの馬」は、それ以前の作品と比べて画面を見つめる緊張感は少なかった。御者の父とその娘の永遠に変わらない様な日々の繰り返し。朝起きて、服を着、水を汲み、馬の世話をし、ジャガイモを食べ……。しかし、全く同じ繰り返しではない。彼らの場合、一つずつ大切なものを失っていく。馬の働きを失い、井戸が涸れて水を失い、しかし余所に行くことも出来ない。 |
|||||||